快く生きる日々 No.33 渡辺照子
人の応援・支援 ~「ヘルプ」と「サポート」の中間的エリア~
この3年間、社会人として地元の国立大学に在籍し、コーチングの修士論文執筆に取り組みました。最初の2年間は、一人8ヶ月のコーチングを6名の方におこなって記録し、最後の1年で執筆。
先日、ようやく書き終えました。論文の最後の「謝辞」には、親身にご指導くださった教授陣、実験のためにご協力くださった組織の方々、実験に応じてくださった6名の方々、分析のためにご協力くださった方々、応援してくださった友人達、そして、健康を気遣ってくれた家族に、深い感謝の思いを言葉に表しました。皆さんの支えがなければなし得なかったことと、心底ありがたい気持ちでいっぱいです。
ようやくできあがった論文ですが、今回、書くことを進ませてくれた印象深い体験があるので、ここに記します。
私は日頃、コーチングのコーチという職業をやっているのですが、クライアントさん達の目的やゴールは違えども、何をやっているかというと、「相手の方が、自分で、目指すところに到達する、そのプロセスと結果を応援すること」です。私が何か手出しするのではなく、相手の方が、自ら進んでくれるようにと関わるのです。
ところで、私が、「ヘルプ」と「サポート」という言葉を区別して捉えるようになったのは子育てコーチングを学んだ際です。赤ちゃんは生まれたばかりは、自分では何もできない。だから、親は全てやってあげる。つまり完全に「ヘルプ」します。しかし、日を追うごとに自分でできることが増えていくので、親はやってあげる手をだんだん引き、「サポート」をしながら、我が子を自立へと導く。大事なのは、子どもの成長に合わせて、「ヘルプ」の度合いを減らし、「サポート」の度合いを高めて、完全に自立できるよう、自分で行えるような環境をつくっていくということ。「ヘルプ」をずっとやっているとどうなるか・・・。子どもは、自ら進むその体験を味わえず、親がかりなままになるので、自分の人生を生きることができずじまいになってしまうというのだ。
私は、我が子に自分の人生を生きて欲しいので、上記の考え方に賛同し、やってあげたくなる気持ちを、ぐっとこらえ、時にはそのこらえることの苦しさと闘いながら、我が子育てをしてきた気がします。
さて、論文を書くというプロセスは、私にとっては、フルマラソンを初めて走るような体験でありました。「書き終える」というゴールだけは明確でも、そのイメージは、時に揺れ動き、どのようなプロセスが待ち受けているのかも、皆目予想ができず、翻弄されつづけたという感覚でした。そういう中で、論文執筆の前進を大きくアシストしてくれた二つの出来事がありました。
その1つめは、授業でお世話になっていた、N先生の私に対する関わりです。たまたま、N先生の授業を取った生徒は私一人だったので、毎回の授業はマンツーマンです進みました。N先生に教わっていた授業科目は、私の研究とは直接関係のないものでしたが、私の研究に関心を示してくださり、論文というものをどのように書くのか、授業中に時折ご指南くださいました。先行研究に関して、先生自ら、研究者がアクセスできるサイトにアクセスして、先行研究論文を調べて、リストをプリントアウトした用紙を、授業の時に私に渡してくださいました。この時をきっかけに、私は大学の図書館に通い、先行研究を探索し始めたのです。頭ではやろうやろうと思っていたけれど、仕事との両立がなかなか思うようでなかったところでした。
そして、2つめは、私の元に、彗星のように現れて、統計分析手法を教えて導いてくださったHさん。Hさんは、統計の専門家でいらっしゃり、私はその統計方法を全く知らなかったので、ティーチングしていただいた。この後のHさんの私に対する関わりが効きました。私が書きたいのに書けず逡巡している様子を捉えたHさんは、「とにかく書き始めようよ。」と力強く促してくださり、私に何をどう書きたいのか、ヒアリングをし始め、そのヒアリングを元に、論文の一部を書き始めてくれたのです。そのときHさんが書き始めてくださったことをきっかけに、自分がそれまでに書いてきたところと突き合わせながら、自ら書く軌道を手に入れることができたのでした。
私は、コーチという職業においても、子育てコーチングの考え方においても、人が自ら行う・自立するために、自分自身は、「ヘルプ」ではなく、「サポート」を心がけるのだ、というのをかなり強く意識してきたように思います。その私にとって、N先生とHさんの関わりは、濃厚な「ヘルプ」であったのですが、それが私の前進に大きなきっかけをくださった。それを味わったのです。
私の中に生まれた思いは、私の中の、人を応援する関わり方の中に、【ヘルプとサポートの中間的なエリア】を設けてもよいのではないかというものです。実際は今までもそうしてきたのかもしれませんが、意識の中では、「ヘルプをするな!」「ヘルプを最小に!」「ヘルプをやめて、とにかく早くサポートに移行せよ!」というような鐘を自分に鳴らし続けてきたように思います。
人が自立して生きていくためには、人にヘルプやサポートを求める力が欠かせないともいわれます。何が何でも自分でするのではなく、必要な時には、周りに頼る力が、自立して生きるには肝要であると。そうなると、する方もされる方ももっと、「ヘルプ」と「サポート」の間を、緩やかに軽やかに行き来して良いのではないでしょうか。
私は、当面の間、【ヘルプとサポートの中間的なエリア】というものを探索していこうと思います。今後探索が進むにつれ、私の応援や支援の内容は、今以上に充実してゆきそうな、そんな予感がしています。

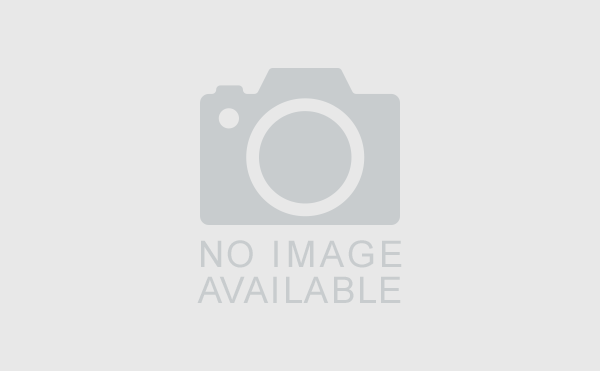
ヘルプは 杖
サポートは 眼差し
かと
柴田さん、コメントをどうもありがとうございました。
(返信が遅れてすみませんでした。)
ヘルプは、杖。
サポートはまなざし。
「杖」と聞くと、「転ばぬ先の杖」という言葉を思い出します。
親が子どもに、転ばぬ先の杖を差し出し過ぎると、子どもは転び方を学べないし、
起き上がり方も学べない。
と、子育てコーチングを学んだときに、講師から教えてもらいました。
一方で、先日地元の高校の入学式に参列しようとしていて、でも、
その二日前に軽いぎっくり腰になってしまい、「起立 → 一同礼 →着席」に
対応するには、「杖」がないと、自分一人では座ったり立ったりできないと、「杖」の存在を必要とすることもありました。
杖よ、杖よ、ああ杖よ
なかなか意味深いなあと思います。
私は、これまでサポートは、「相手の話を聞いたり、問いかけたりしながら、
一緒に考えること。」と表現してきました。
柴田さんの「サポートはまなざし」この表現は、私は初めて聞きまして
早速取り入れさせてもらおうと思いました。確かに、
「親」という漢字は、木の上に立って見る → 見守る
って聞きますものね。
人育てには、「ヘルプ」と「サポート」が要る。
柴田さんのコメントにより、改めて感じることができました。
どうもありがとうございました。
渡辺さんへ
さすが専門的な分野を極められるだけあってヘルプとサポートの区別はチョー難しい🤭
でも頭の中を色んな考えが駆け巡って、親の気持ちや自分の子供の頃に生まれたであろう気持ちを想像してみるうちにひとつの答えが出てきました。
それは「認め合い、学び合い、応援し合う」の「合い」についてです。
これまで私は「合い」という意味は、お互いが相手に対して「それ、すごくいいね」のような同意の感情や言葉で双方向に掛け合うものと思っていました。そしてそれには複数の存在が必要となります。
しかしそれとは別の用い方として、たとえば水を温めるとそれと同じ熱量で物を温めることができるように、人は相手から受けた愛情と同じ熱量の愛情を自分の無意識の中に蓄え、やがて誰かにお返ししていくという発想です。愛情をかけた方も同じで、誰かからの愛情を受け取るための余裕が同時に生まれます。
うまく説明できていないかもしれませんが、こう考えた方が渡辺さんのコラムがより生きてくるように思われました。
そんな「合い」が「愛」となって大きく膨らませていけたら素晴らしいですよね。(うまく落ちがつきました😊)
コラムの中に散りばめられた渡辺さんのたくさんの感謝から生まれた発想です。感謝。
追伸
執筆といえば、僕もFBの中で小説を書きはじめました。渡辺さんにもご覧いただけたようで恐縮です。今読み返せば結構な乱筆で恥ずかしいのですが、今回のような心の「合い」を描いていけたらと思っております。
おっくん
おっくん、いつもコメントをどうもありがとうございます。
(返信が遅れてすみませんでした。)
「合い」が「愛」となって大きく膨らませていけたら素晴らしい
おっくん、おっくんのコメントの究極は、上記のところですね。
確かに、ヘルプとサポート、する人からされる人への視点だけではなく、
「合い」や「合う」そして、英語で言うところの、「Pay it Forward」の意味合いの
意味深さをおっくんはコメント内容に込めてくださったのですね。
おっくん、「合う」「愛」に関して、最近思ったことがあります。
友人のすごく愛していたワンちゃんがなくなりました。
友人の悲しみがおおきくて深くて・・・。このことは何から来るのかと考えたとき、
「合う」や「愛」の深さの分だけ、別れのつらさやいたみがやってくる。
では、別れやつらさを避けるために、「合ったり」「愛したり」しないのかというと
人が生きるとは、やはり、「合う」だな。「愛」だな。って思います。
筋道だった表現ではないのですが、
おっくんは読み取ってくださるだろうと信じて、書き終えます。
小説、楽しく読み続けさせていただきます。
渡辺さんとふたりの先生方の関わり方が、とてもほほえましい気がしたので、どうしてそんなふうな心の対話ができるんだろうって思い、考察してみました。こういうことが自然に、普通にできるといいですね。
おっくん、コメントどうもありがとうございます。
こういうことが自然に、普通にできるといいですね。
↑そのように思っていただけて嬉しく、
そして、そうなるといいなと私も願います。
渡辺さんへ
ご無沙汰しております。中川です。
久しぶりに渡辺さんの近況を拝読しました。
国立大学で論文を執筆されていると初めて知り、
「やはりそうだったのか」という驚きとともに、深い感慨を覚えました。
「ヘルプ」と「サポート」について、赤ちゃんの成長に合わせて説明されていたことで、理解が一層深まりました。普段は無意識に行っていることですが、その違いを意識し、相手の状態や状況、さらにはお互いの関係性に応じて関わり方を調整することの重要性を改めて感じました。
久しぶりに身が引き締まる思いです。
ありがとうございます。
中川さん、コメントをどうもありがとうございました。
(返信が遅くなってすみませんでした。)
中川さん、ブログ内容をお受け止めくださり、感謝いたします。
中川さんのおっしゃいます、
違いを意識し、相手の状態や状況、さらには お互いの関係性に応じて
関わり方を調整する
上記のことこそが肝要なのですよね。
関わり方を調整するプロセスは、簡単ではない。でも自分自身を成長させてくれる
素晴らしい道のりでもあるので、ごっつんごっつんぶつかりながらでも
やって行きたいなあと思っている今日この頃です。
中川さん、どうぞ日々ごきげんにいらしてくださいませ。
渡辺さんへ
波呂です。書き込んで良いのがどきどきしながら書いてます。資格その他でまずければ、削除お願いします。
アドラー、でしたか、歩み始めたクライアントに「カウンセラーのおかげです」と言わせたら失敗だと。つまり、このクライアントはまだカウンセラーに依存していて、自分の力や自立感を得ていない。
そういう意味で、私も人のお手伝いするときに、迷いがあります。どこまで主導して良いのかとか。しかし一方で、納期とか成果物の仕上がり精度といった事情があるのも、これまた事実。
そんな中、渡辺さんの
—
「ヘルプ」と「サポート」の間を、緩やかに軽やかに行き来して良いのではないでしょうか。
私は、当面の間、【ヘルプとサポートの中間的なエリア】というものを探索していこうと思います。
—
ヘルプかサポートか、あるいはヘルプからサポートへの移行、といった二律背反的な考え方ではないのですね。緩やかに軽やかに「行き来」できる「中間的なエリア」、言葉は優しいけど、とても刺激的な考え方だと感じました。
「探索」で得られた知見、とても楽しみにしています。僕もまた並行して、その真似ごとをしてみようと思えました。そこに何かが、ありそうな予感です。
波呂さん、コメントをどうもありがとうございました。
(返信が遅くなってすみませんでした。)
お書き込みいただき、とても嬉しいです。
波呂さんがお書きくださった、
アドラー、でしたか、歩み始めたクライアントに「カウンセラーのおかげです」と言わ
せたら失敗だと。つまり、このクライアントはまだカウンセラーに依存していて、自分
の力や自立感を得ていない。
のような内容を、コーチングのコーチをしている私も、これまでの学びの中で、
教えてもらったことがあります。
実際、「自立している」とか、「自立できた」という状態は、本人が生きることを
良しととでき、生きることを味わい楽しめる、本人の中から力が湧いてくる境地だと思うので、その状態を相手の方に味わってもらいたいな~っていう思いがあります。
しかしながら、どういうのがよいのか、お仕事等の場面では、
「納期とか成果物の仕上がり精度といった事情」が確かに生じますよね。
波呂さんも日々探索をおすすめくださるとのことですので、
お互いに探索して、結果を話し合いたいですね。
それにしましても、この度は、こころより、どうもありがとうございました。