「あるもの」をつなぐ No.40 シンイチロウ
解決志向のチームマネジメント 5年間を振り返って
本ブログを書き始めて5年が経ち、40回目を迎えました!
なんとなく区切りがいいなあと思ったので、この5年を通じて、解決志向のコンセプトで運営してきたチームが、何をして、どんな姿になったのか。そして、どんなことに気づいたのか、軽くまとめてみたいと思います。一つでも使えるものが見つかれば幸いです。
1. 解決志向への「スイッチ」
ぼくは当初、誰が見ても問題と思われる行動を繰り返すメンバーに、問題を直すアプローチ、つまり従来のマネジメントや指導をして、行き詰まっていました。結果、ぼくもメンバーも疲弊してしまったんです。どんどん関係が悪化しました。
それで、どうしようもなくなって、開き直った先に、解決志向へ舵を切ったんです。計画的に切り替えたわけではないです。メンバーとの関係が悪化して、困りに困って、「これって何か違うよな。メンバーとは協力関係をつくらないと成果なんて出せないよな」と思い直して、「解決志向のスイッチ」が入りました。
そして、「相手志向」で「あるもの」に目をむけて、解決へ向かう姿勢に切り替えたんです。問題を置き去りにして、メンバーの抱える事情(家庭の事情や気持ち)を知って、踏まえて、既に持っている「あるもの」(出来ていること・関心ごと・意欲)を活かす道を選び、実践していきました。
2. マイホーム(朝会)づくりと個性の開花
この実践の土台となったのは、毎日続けていた「朝会」です。これを業務連絡だけでなく、不安や気持ちまで話せる「安全基地」として継続した結果、チームは気持ちまで含めた互いの状態を知り、協力し合う強い関係性へと変化しました。この土台の上で、メンバーの個性の開花が始まりました。
例えば、「仕事をしない」と見なされていたコイデさんは、環境への関心を仕事につなげた結果、全社環境プロジェクトのリーダーとして大活躍し、本部長賞まで獲得しました。
また、仕事が計画どおり進まず、仕事を任せきれないアリオカさんは、ぼくと一緒にリモート同席していると「うまく仕事が進む」という観察に基づき、「リモート同席スタイル」を採用して計画達成していきました。今や全社発表会のリーダーをお任せして活躍されています。
さらに、組織として重要なデジタル業務に強く抵抗したチュウさんについても、意欲のスケーリングを通したら、「新しいことを学ぶ意欲」という見えないリソースや「会社への貢献意欲が高い」ことに気付きました。新しいデジタル技術は、会社に大きく貢献できるテーマであるという意味を伝えたことで、チーム内でデジタル推進を引っ張る存在にまで育ってくれました。
3. 「気持ち」を知る大切さの再認識
しかし、チームは感情的な課題に直面します。メンバー間の嫉妬からくるコミュニケーションのトラブルが発生。チュウさんが苦しんでいることに気づきませんでした。
当時、ぼくのチームは新しい仕事を担い、高い目標達成を求められていました。なので、気持ちまで聞く「朝会」を業務効率優先のコミュニケーションへ移行したんです。朝会を進化させようと思ったんですね。結果、気持ちまで聞くことが減ってしまいました。
そのツケがきて、チュウさんが、ぼくのチームから異動希望を出すくらい、つらい状況まで追い込んでしまいました。すぐにフォローしたので、異動まで至らなかったのですが、組織運営において、仕事の状況だけでなく「気持ち」まで知ることの大切さを痛感させられたのです。
4. メンバーの気持ちを乗せた戦略をつくる「攻め」
解決志向のチームマネジメントはさらに進化します。メンバーの気持ちを聞く中で重要なことは、「大切にしていること」を聞くことでした。大切にしていることは、メンバーごとに違うし、1つだけでなくいくつもあります。
最も好ましいのは、仕事とメンバーの大切にしていることが関連づいていて、仕事を通じて、その大切にしていることが成就されていくことです。解決志向のチームマネジメントとしては、ここが真骨頂であり、攻めの部分です。
メンバーが大切にしていることは、朝会での報連相、業務中の雑談、仕事の進め方の観察、一緒に食事をしている中で垣間見えることがあります。このような各メンバーが大切にしていることを起点として、組織目標を達成する戦略をつくっていくと、メンバーの大切を成就できるマネジメントの準備ができます。
チュウさんはデジタル業務を進める中で、デジタルに対する興味が高まり、組織貢献を実感し、自信を育ててきました。キャリア志向の高いチュウさんにとって、デジタル業務は大切な存在になっていきました。
2023年、デジタル領域の拡張として、「デザイン業務への生成AIの活用」という新しい挑戦的なテーマを設定しました。このとき、このテーマが成果につながるか未知数でしたが、僕らのチームが進化し、5年、10年会社に貢献していくには、今やらねばと考えていました。
そしてチュウさんの興味関心に沿って目標を達成できる戦略をつくり、チュウさんと共有して、しっかりとチュウさんの気持ちも乗せた戦略に仕立てることができました。こうして、テーマと個人の興味や大切が結びつくことで、自発的に、かつ強い推進力でテーマに取り組む準備ができました。
5. 主体性をもった挑戦を支える「守り」
ただ、挑戦には失敗や遅れがつきもの。途中でうまくいかない状況が続いて、モチベーションが下がったり、目標達成できないんじゃないかと不安になったり、こんなことやってて意味があるんだろうかと悩んだりします。
なので、メンバーのモチベ低下や不安、悩みを払拭する「守り」が必要です。「守り」としてリーダーができることは、日々の報連相や期末評価フィードバックなどで、テーマに対する興味を高め続ける発信をしたり、やってることの貢献(意味)を伝えたり、失敗しても「いつでも味方だよ」という姿勢をとり続けることでした。メンバーは鼓舞されるというより、内側の興味や意欲が再燃し、主体性を継続することができます。
補足なのですが、会社にとって都合の良いように「成長」とか「キャリア」の目標を社員に設定させ、その目標を達成するために、仕事を与えるやり方と「ポテンシャルアプローチ」とは違います。「ポテンシャルアプローチ」は主体性を前提としたアプローチです。
この入り口をはき違えてしまうと、メンバーは「組織という場を使う個人」というより、「組織に使われる個人」になってしまい、主体性が損なわれてしまいます。解決志向のチームマネジメントは、主体性を大切にします。
6. 「窮屈なマネジメント」から「自分らしいマネジメント」へ
5年間の道のりを振り返り、今、強く大事だなって感じるのは、リーダー自身が「窮屈なマネジメントの制服」を脱ぎ捨て、自分らしさを中心に据えることです。
会社から与えられた「こうあるべき」という役割や、出来合いのマネジメント手法に縛られる必要はありません。まずは目の前のメンバー一人ひとりの個性と向き合い、自分自身が見て、関わって、体験して感じたことを大切にしながら、十人十色の仕事の進め方をクリエイトしていくことが望ましいと思っています。
また、小さなことでもメンバーの気持ち(モヤモヤ、シコリ)を分かる機会は、「感情的なボトルネック」を抑制し、メンバーの力をスムーズに流していくのに必要不可欠です。
さらに、リーダーは「いつでもキミの味方だ」という姿勢を貫き、主体性を前提とした「ポテンシャルアプローチ」をとり続けることで、メンバーは輝き始めます。
7. 最後に
2026年には新しいメンバーが加わります。次はどんな景色を見せてくれるんだろう。いまからワクワクしています。来年もぼくらのチームを見守っていただけるとありがたいです。
それでは、ちょっと早いですが、良いお年をお迎えください

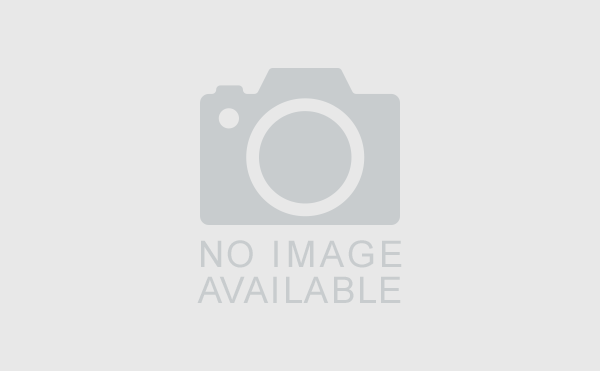
シンイチロウさんへ
5年と40回、おめでとうございます。年月の力を感じています。
「ソリューションフォーカス」という思考回路とは結局のところ、組織を修復するだけでなくそこに携わる人(特にSFを用いる人)たちをとてつもなく強靭に、且つ自由と柔軟に育てていくことが想像されます。文字で表すのは難しいですが、確信に満ちた文章を拝見して「なるほどそういうことか」と感じてしまいました。
またそこで獲得したものは、ソリューションフォーカスを実践していく中での副産物という概念だけではなく、ひょっとしたら〈そのこと〉こそが本来の目的であり、それに気づくための悩みであったり、迷いであったり、時には喜びであったりするのかなあと。
いやー、これが正解という答えもないし、ここまでというゴールもない。少し手を抜くと積み上げたものが試される場面もあるでしょう。そんな日々の中でもシンイチロウさんにはあきらめなかったし、それを支える仲間がいることはとてもうらやましいことです。よき人生に乾杯ですね。
自分ながら久しぶりに哲学的なコメントに出会えたことも楽しかったです!来年も期待しておりまーす♪良いお年を!
おっくん
おっくんへ
コメントありがとうございます!おっくんの毎回のコメント、めっちゃ力になってます。おかげさまで40回まで書き続けることができました。
以前も言ったかもしれないですが、勝手におっくんはチームメンバーの一員だと思っています♪
読んでくださっているみなさまにも感謝しております。ありがとうございます😊
この「少し手を抜くと積み上げたものが試される場面もあるでしょう。」というコメントなんですけど、ドキッとしました。こんな場面ばかりです。
「なんか良い流れになったぞ」と思っても、次の瞬間、全く逆になってる💦だからこそ、チーム(組織)でリズムを整えることが大事なんだと思っています。
最近、とてもうれしいことがあります。メンバーから、
「うちのチームは補い合うチームだから」
「うちのチームが評価されることが大事だから」
「うちのチームはどんどん進化している」
「うちのチームが他部門を支えてあげないと」
以前のような「自分が自分が!」という意識から「うちのチームが良くなるには」というふうに意識が大きく変化しました。チームと自分が一体化しちゃったような。
この言葉を聞くたびに、「やったー♪」って心の中でつぶやいています。
またおっくんのコメントに触発されて、長々書いてしましました。
来年もよろしくです〜
シンイチロウ
チーム全体の進化の様子も素晴らしいですね!
そうですね、青木さんのおっしゃる通り。シンイチロウさんの辞書に「後悔」の文字はない!ね。