SF伝道者の四方山話 No.41 青木安輝
たった一言で光が差すとき
ある勉強会の懇親会。初対面の人が多く、「どんな縁でここに来たのか」みたいなおしゃべりの輪に入った。僕と同年代のある女性が、以前手伝いをしていた団体での仕事について「そこではタダ働き同然で大変なことやらされてホントに嫌になっちゃったのよ~」と話し始めた。その女性は絵の専門家で、団体が主催する通信教育講座で素人が提出してきた絵を見て、感想と教育的コメントを書くという内容だったそうだ。絵の数が膨大で初心者へのコメントは気を遣うので、ものすごく時間がかかった。それなのに貰えるお金はスズメの涙ほど。だから、ずっと損したと思っていたと口を尖らせた。
同情コメントを思い浮かべながら、この話はどんな結末になるんだろうと思っていたら、そこからその人の顔が急に輝き始めた。「ところがね(ニヤリ)。この話をTさん(この勉強会の主催者)にしたら、『それはとても貴重な“フィールドワーク”ができたってことですよね。』と言ってくれたのよ!私もう本当に嬉しくなっちゃってさ。だって、こき使われた割に正当な対価はいただいてないって気持ちは確かにあったけど、実はすごくいい絵も沢山あって、その仕事自体は面白かったのよね。で、よく考えたら学んだことも沢山あった。『こき使われた』という記憶のレッテルを『貴重なフィールドワークをした』に変えたら、本当にそうだわ!って思えたのよ。だからそれ以来そのことが良い思い出になっちゃってね。それからTさんとの縁が深まって、今日もここに来てるの♪」と、聴いているこっちまで気持ちが明るくなる楽しげな声になった。
「大変でしたねえ、ひどい団体ですねぇ」という同情でも、「きっとそれも意味があったんですよ」等の陳腐なフレーズでも多分それほどの効果はなかったと思う。「フィールドワーク」という肯定的かつちょっと玄人っぽい意味づけが、アカデミックな背景をもっている専門家の彼女にはジャストフィットしたようだ。その後、彼女は「フィールドワーク」という言葉を何回も繰り返した。
僕も人からもらった一言でスーッと気持ちが軽くなって前を向き直した良い思い出がある。僕の人生の大事な一部であるゴルフで、やっとシングルハンディになってこれからという時に「イップス」病にかかってしまった。クラブを振り上げたところで身体がジーッと止まってしまい、どう振り下ろしていいかわからずパニックになる。仕方ないのでエイッと無理やりクラブを地面に向けて叩きつけるので変なショットになる。当然スコアは酷くなる。直そうと焦るほど、その症状が酷くなる。色々試しても効果がなく、ごまかしごまかしプレーしている自分が情けなくて、もう未来はない、ゴルフやめるしかない・・・と思い始めた。そんな時、ある先輩(全国大会でも優勝している素晴らしいゴルファー)にそのことを話したら、すかさずこう言ってくれた。
「青木君ね、イップスはうまくなる人がなるんだよ。」
これを聞いた瞬間、サーッと自分の頭の中、体の中が綺麗になる気がして、体が軽くなり、顔がほころぶのが自分でもわかった。な~んだ、俺はこれからうまくなるんだって素直に思えてしまった。たった一言。それ以上は必要なかった。イップスは単なる通過儀礼だからいつか直るという気持ちになれた。すると色々工夫したり教えてもらったりしたことが効果を現し始めて、症状は消えていった。今でも「うまくなる人がなる」の声のトーンやその時のスーッと気持ちが軽くなった感触はよく思い出せる。
多分これを読んでらっしゃるSFブログ読者の皆さんも、「この一言に救われた」あるいは「自分の一言が相手を救ったようだった」という体験がおありになると思う。
自分の頭の中だけでずっと考えていると、同じ捉え方しかできずに否定的な気持ちが固定されてしまうことが起こりがち。それはわかっているからと自分の努力で違う捉え方をしようとすることは可能だ。だけど、無理やり肯定的に思い直そうとするプレッシャーは逆効果になることも多い。やはり、人と話している中で「×」と思い込んでいたことが実は「〇」だったという視点を相手から突然もらえた時に光が差して、視界が開ける感覚になれることが多い。だから信頼できる人に頭の中のあれやこれやを話すことって大事だよねというのがこのブログの結論・・・なのだが、上記のような効果的な一言が発生するための条件とは何であろうかとさらに掘り下げてみたい。
コミュニケーション(言葉)の分析をして、専門家気質の人には「フィールドワーク」のようなあまり一般的でない専門用語で価値を示すことが大事とか、(イップスという)症状の持ち主がこれから良くなるという文脈をつくる表現を試みることが大事とか、訴えを傾聴した後すかさず言うなどと技術的なポイントを見つけることもできる。しかし、そういうもっともらしいテクニカルな解説はどうも後付けのような気がする。「リフレーミング」などと技の名前を知ることで、「なるほど、捉え方の枠組みを変えれば良いのだな」とわかった気になれるが、それもどうも何かが抜け落ちている気がする。
そこで、Tさんと僕のゴルフの先輩の共通点て何かなあと思い返してみる。まずお二人とも人の話しに耳を傾けてくれる人だ。そして上から目線で勝手に決めつけるようなモノの言い方をしない。だから、自分のことを話してみたくなる。よく聴いた上で反応してくれるから、ちゃんとこちらのことをわかった上で何か言ってくれると思えるので、その意見を聞いてみたくなる。つまりこちら側の心のモヤモヤに対して新鮮な切り口を提供してもらえるかもしれないという無意識の期待が高まる。
それからTさんも先輩も穏やかで中立的な印象を与える。感情的に人の悪口を言うのを聴いたことがない。それはあえて悪感情を抑えているというよりも、むしろ人の欠点などが小さく見えるくらい大きな視点でものを見ているので、近視眼的に「これがダメ!」というところに飛びつかない・・・のではないかと僕には見える。
だから、人が愚痴をこぼしたり、何かの悪口を言い始めたときに、その悪ストーリーに一緒に入っていかない。話はよく聴くけど、問題点を一緒に拡大するような反応をしない。そして、問題の話しをしている本人の背景とか、話されている内容が位置する大きな背景を見ているのだと思う。だから「絵の専門家にとって、意欲あるアマチュアの作品に数多く接してそれらを批評することは、専門家としての感性が研ぎ澄まされる大切な現場なのではないか」という発想ができる。また、「半べそかきながらイップスでゴルフやめたくなったと言っている青木君も、それだけの情熱を持っているなら多くのトップアマやプロゴルファーが一度は体験するイップスを通過してその先に行けるだろう」という視点にたどり着ける。つまり良いことが見えてくるまで視野を拡大することが「プラスの眼鏡」になっているんだろう。
「傾聴」も「大きな視野でうけとめる」も冷静かつ理性的に行っているように見える行為なんだけど、それらを実行させている根本的動機は「この人に良いお知らせをあげたい」というサービス精神のようなものではないだろうか。SFでは「他者尊重」って言葉にまとめてるけど、自分の存在価値を貶めるようなモヤモヤを晴らしてくれる一言は「あなたは尊い存在ですよ」という眼差しから生まれるのだと思う。
「他者尊重」が大事というのはわかっているけど、しょっちゅう忘れるので、このブログも含めてSFの仕事をするたびに自分にリマインドしている次第です。

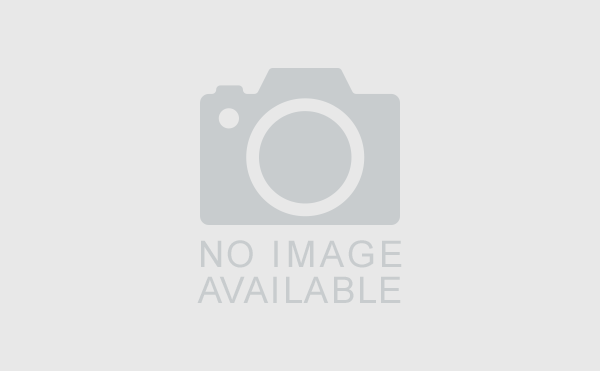
青木さん、いつも楽しく読ませていただいています。今回こそはコメントを!と、揺れる車内でテキスト打ってます^^
ゴルフの話、胸熱リフレーミングでしたね。そのお言葉、私もぜひ拝借させていただきます!
ある出来事が「嫌な過去、辛い経験、、この先も不安」といった意味づけだと(わたしは最近その傾向が強く出ます^^;…)心が負のスパイラルに入ってしまいますね。そんなとき、誰かからのリフレーミングが本当に大きな助けになるなぁと私も感じます。
そう考えると、「なんかイヤだな〜」「私、自分のことこう思っちゃってるのよね〜」みたいなことも、話せるときにはペロッと口に出してみるとリフレーミングのギフトが相手からやってくるかもしれず、大事だなと思いました!
私の「この言葉に救われた」シリーズは思い返すと幾つも見つかりました。一つは仕事に集中できず、首も気分も重くて、「私、カフェに逃げてきた〜」と友人にメッセージしたときのこと。そしたらその友人から「それは逃げたんじゃなくて、自分をリフレッシュさせに来たんだよ」って言ってくれ、一気に気が楽になりました^^
またブログ、楽しみにしています!
こばちゃん、久しぶり~!なんだか懐かしいなあ。
ブログを楽しく読んでくれているのがわかって嬉しいです。
「ギフト」っていう表現はまさに当たってますね。
ある種の関係性の中ではそれが思わず口から出てくるってのが素晴らしいよね。
「起こったことはすべて最高。起こらなかったことはそれで最高」ってフレーズは
僕にとって色々なことをギフトにしてくれてるなあと思い至りました。
また、SFプログラムにご参加くださいね~♪
「このひとなら、自分の話を分かってくれるかもしれないなぁ~」と思ってもらえるような話の聴き方をしたいと思っています。ちゃんと聴くひとって、多分、そういうコトなんだろうなぁ~と、つくづく感じることがあったのです。そんな意味で、今日の話は、大きなギフトでした。ありがとうございます。
~まずお二人とも人の話しに耳を傾けてくれる人だ。そして上から目線で勝手に決めつけるようなモノの言い方をしない。だから、自分のことを話してみたくなる。よく聴いた上で反応してくれるから、ちゃんとこちらのことをわかった上で何か言ってくれると思えるので~というところ。
わたしは、日常で、絶え間なく(笑)2歳~3歳の話を聴いています。言葉の構造もあったもんじゃないし、話の内容が理解できなことを聴き返しても、自分の望むような答えは返ってこないけれど、子どもたちにとって大切な話だと思えば、おとなの話を聴くような気持で、真面目な顔をして聴いています。
子どもにとって、話を聴いてもらうことで【自分の思いをわかってもらった】というのは、素晴らしい体験だと思うからです。
思うようにならなかったり、嫌なことがあったりして、泣いてしまう子どもに対して、その瞬間に、光がさすような一言が言えたら(子どもだから、ほんとうに【一言】ってこと)嬉しいなぁ~と思いながら、青木さんの文章を読みました。
他人のことばかり気になって(ちょっと荒さがし…みたいに)いろんな先生に、言いつけに来る3歳の子がいます。わたしは「ひとのことなんて、いいから、自分のことに集中しようよね。」と、本当は言いたい気持ちがしているけれど、その話題を広げず、批判や判断を脇に置いて、ちょっとだけニッコリしてギュっとして「ふぅん、そうなんだね。」という言葉だけで済ましています。
実は、わかい男子のせんせいが、その男の子に「ひとのことはいいから、いいから!」と、あっさりと言っているのを聴いて(ちょっと笑っちゃったのだけれど)いろいろなせんせいが、子どもに関わるっていいなぁ~って思いました。ですから、これは、まったく深刻な話ではなくて、聴き手としてのわたしの中にある解決したいコトなんだと思います。
彼がわたしに求めているのは、ちょっとだけニッコリして「ふぅん、そうなんだね。」と言ってもらうことではないんだろうと思いながら、彼の奥底にある気持ちを考えています。明日、もし彼が言いつけにきたら、なにか彼が納得できるような光が差すようなひとことが言えたらいいなぁ~と、今思っています。
毎日が聴く練習です。一生をかけても、よい聴き手になりたいと、つくづく思います。
花村さん、コメントありがとうございます!
毎日色々な子供さんたちと接するのってなんだかうらやましいなぁ。
「聴いて聴いて~」ってかけよってくる子がいるなんて♪
そういう子にとっては、花村さんがいるってだけで既に光が
差してるんじゃないですかねえ。植物が自然と光の方に伸びていくように。
花村さんの「聴く」体験のシェア、これからも楽しみにしてま~す。
青木先生へ
おはようございます。
「他者尊重」への深掘りブログ、ようやく秋らしくなって出会い季節のはじまりにぴったりですね。
普段忘れがちなこのフレーズを再びインプットして、身の回りの生活を見回してみると新しい世界が見えてくる予感がしてきます。あの人にも、このメールにもと「ちょっと気の聞いた言葉」を探してみようかなと思いました。
なんだか楽しくなりそうです。
おっくん
おっくん、コメントありがとうございます。秋の始まりにまわりの人への「ちょっと気のきいた言葉」を探すって、なんだか高尚じゃないですか!自分世界で完結してしまう趣味もいいけど、他の人の世界にプラスの眼鏡をかけて入っていって光るものを見つけるってのは、ダイナミックですねえ。