SF伝道者の四方山話 No.39 青木安輝
たった一つの質問で有効な自問自答を促す
20年前に初めて欧州のSF活用事例共有大会SOL Worldに参加してからコロナ前までは、毎年のように欧州に行き、色々なソリューショニストと交流しました。その中の一人にブルガリアのプラーメン・パナヨトフ博士(Dr. Plamen A. Panayotov)がいます。スキンヘッド同士だからか、なぜか会った瞬間から気が合いました(笑)
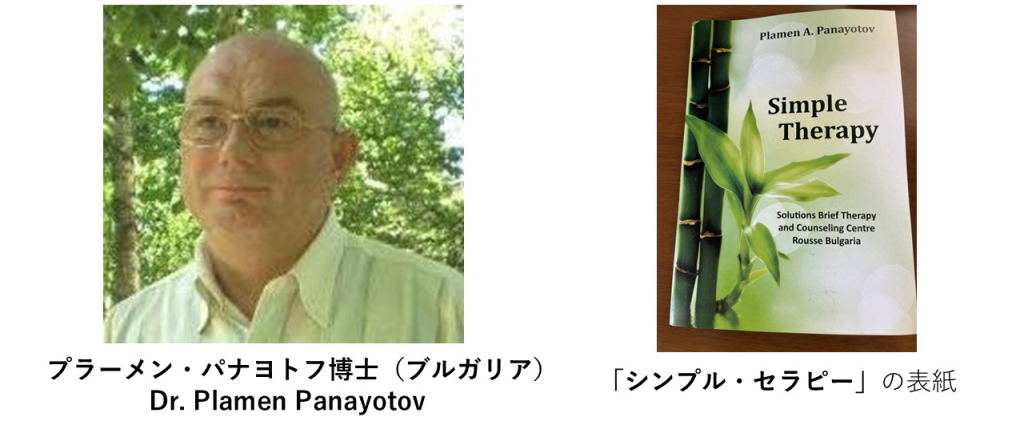
精神科医でありSF実践家である彼が考案した“Simple Therapy”という手法は、最初にたった一つの質問をすることで、相手が抱えている問題に関する語りを誘発し、あとはそれを傾聴していき、相手の自問自答を深め、最後は本人から自助の方法を引き出すというものです。支援者である聴き手側の解釈や勝手な想像を徹底的に排除して、本人の語りを主軸とする会話でサポートする方法です。
そのたった一つの質問というのは・・・
「今、私からどんな質問をされたら一番役に立ちそうですか?」
というものです。これって、聞かれてみると、本当にいろいろ考えるんですよね。「今日は何について話したいですか?」だったら、ぼやっと「・・・について」と言えばいいだけなんですけど、「一番役に立つ一つの質問」て何だろうと考え始めると、自分が抱えている問題や課題に関して、様々な角度から考え始めます。そして、ここを大切にしたいという切り口に関するキーワードが浮かんでくると、遠回りせずに最初からかなり核心に近いところに意識が向かう問いが組み立てられます。その時点で既に回答らしきものもある程度は浮かぶんですけど、実際にその質問をされてみると、さらにグンと内省が深まります。
昨晩「やっちゃんのおしゃべりCafé」で、この「シンプル・セラピー的対話」の体験会をしたのですが、皆さんが口々におっしゃったのが、「自問自答はよくするけど、自分で考えているだけだとどうどう巡りになってなかなか深まらない。だけど、こうやって自分が考えた質問を人から聞いてもらうと、それに応えて語るうちに新しい領域が拓けてくる。」ということでした。
ある参加者の方が最後のシェアでこうおっしゃいました。「このやり方で質問してもらうと、質問が(自分と相手の)真ん中に置かれた感覚になります。」この方がそう言った意味あいは、「普通は人から質問されると、その相手に対する回答義務みたいなものが生じて身構える感覚もあるけど、こんな風にただ質問がそこに中立的に置かれた感じになると、気張らずに真性に自分と向かい合える」といったニュアンスに僕には聴こえました。
一人でする自問自答はどうどう巡りになりやすい。だけど、人から質問されると、その人の考えや捉え方が投影されて、誘導されるような力が働くので鬱陶しい。この2つのデメリットを克服して、自問自答を深める支援をする試みとして考えられたのが、このワンクエスチョン・セラピー(Simple Therapyの別名)と言えます。
プラーメンがこの手法を編み出すきっかけとなったのは、父親と一緒に来院した7歳の女の子との面談だったそうで、それを要約すると以下のようになります:
患者の7歳の女の子は、先週学校で2時間目になると吐くというのを毎日繰り返していた。それを聞いて、プラーメンは例外質問やリソース質問などSFを駆使して解決に向かおうとした。しかし、父親がその類の質問はダメだと拒否。「原因」を徹底的に分析しないとダメだと思い込んでいて頑なだった。
途方にくれたプラーメンは、仕方なく解決志向セラピストであれば普通はしない問題志向の質問をした:
博士:「では、お父さんはこの症状の原因は何だと思いますか?」
父親:「担任の先生が体罰をするんですよ。娘はそれを拒否したいけど言えないから、吐くことでそれを表してるんだと思います。だから転校を検討中なんです。」
博士:「なるほど。で、先生はなんとおっしゃってますか?」
父親;「先生は『お母様が間違った方法で娘さんに薬を与えているからです。薬のせいです。』と言ってました。」
博士:「なるほど。で、奥様ご自身はなんと?」
父親:「妻は『祖父母が私たちが留守の間に変なものを食べさせたからだ』と。」
博士:「なるほど。では、おじいちゃんおばあちゃんはなんと?」
父親:「『母親が消化のいいものを食べさせてあげないことが原因だ』って言ってます。」
博士:「なるほど。」(ここで女の子本人に向かって)「お父さんはあなたが吐いてしまうことの原因を知るのがとっても大事だと言ってるのね。で、あなたは自分ではどうしてだと思う?」
本人:(しばらく無言で考えたのち)「・・・あのね、一回目は”たまたま“だったと思う。で、その次からはそれが”クセ“になっただけ。」
博士:「じゃ、どうしたらいいと思う?」
本人:「一週間くらい朝ごはんを抜けば、お腹に吐くものがないから大丈夫だと思うわ。」
博士:「なるほど!」
そして、博士は父親と相談して、この本人のアイデアを採用することにした。後日父親から報告されたところによると、朝ごはんを抜くのを3日続けたら、吐くことがなくなったので、本人が「もう朝ごはん食べても大丈夫だと思う。」というのでその通りにした。症状は再発することなく、問題は完全に解決!
この面談で、プラーメンは本人以外の人が勝手に問題の原因を考えても的外れになる確率が高いこと、本人は本人なりの考えをもっていて、それを丁寧に聴くことが大事であることを痛感したそうです。なんと7歳の女の子でも自分で最適の解決法が思いつくということに深く感銘を受けたとのこと。
そこで、ソリューニストが大事にしている「不知の姿勢(not-knowing)」を極限まで推し進めてできたのが、このワンクエスチョンで進める対話法だったのです。プラーメンも全てのケースでこの方法が有効であるわけではないと言ってますし、時にはknowingで「こうすればいいんだよ」と直接的に助言することが有効な場合はもちろんあります。
しかし、内省を深めること自体がその人にとって大切なことである場合には、質問自体も本人に考えてもらって、あとは傾聴するだけというこのやり方はとても有効であるようです。聴き手の考えを投影させずに「あなた自身はどう考えていますか?」の類のことを聞き続けることは簡単ではないかもしれませんが、支援するつもりがただのどうどう巡りになってしまう場合には試してみたらいかがでしょうか?
昨晩の体験会に参加された方々のアンケートへの回答からいくつか紹介してこのブログ記事を締めくくりたいと思います。今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました!
【SFブロガーの遊び部屋(7月)アンケートより】
*シンプル・セラピーの質問は、ほんとにシンプルだけど本質をついている質問だった。
*相手が、自分自身で問いを立てて、自分自身で壁打ちをしていくやり方がとても良かったです。
*話が意外と深まるし、確かに人生の主人公は自分なのだと再確認できる感じ。
*考えを深めるときに聴き手がいることの効用を実感した。(効果を最大化する聴き手について考えた)
*相手に興味関心を向け、大いなる好奇心を持つことで、潜在的な可能性を引き出す。集中とリラックスのバランスが、とてもいい!
*この質問は、良いワンダウンポジションの質問だと思いました。「どんな質問をされたい?」って聞かれたら上から目線の気がするし、「どんな質問がいいですか」もなんか硬くて突破しづらい感じがする。役に立ちますか?でもいいけれど役に立ちそう?って微妙だけど最高だと思う。だから、こう訳してくれた青木さん最高!だと感謝します。
*ビジネスシーンを含め様々な場面でステルス的に使えそう!
*久しぶりにソリューションフォーカスの雰囲気が味わえてとても良かったです。またよろしくお願いします。
*参加者の皆さん、前向き、明るく、温かく、学ぶ意欲、成長意欲全開!まさに、AOKIs WORLDでした。

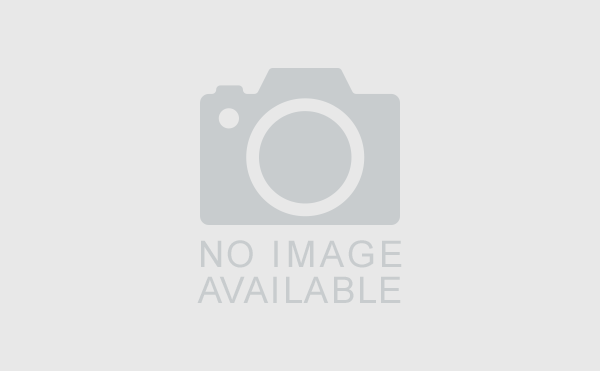
青木先生へ
外は35度、頭の中も40度に。
またもや新しい領域にメモリーも不足気味で、おっくんGPTもそろそろアップグレードしなきゃあね😅
「今、私からどんな質問をされたら一番役に立ちそうですか?」も続編の「今、あなたの人生がここにいる私たちに問いかけていることは
何だと思いますか?」のどちらからも優しい人のぬくもりを感じています。言葉にすれば一息で終えるセンテンスにも色んな知恵が詰まっているのを知るとセラピーというものの奥の深さを感じています。
また遊び部屋の参加者の皆さんの声を拝見して上記の言葉の持つ力の大きさも伝わってくるようです。単に言葉をコピーして使うのは簡単ですが、その効果をうまく引き出せるかどうか今の僕には自信がないですね😁
ひとつ質問してもよろしいでしょうか。
SFとセラピーの関係性も理解しないままで申し訳ないのですが、セラピーと聞くと、プラーメン博士も精神科医であるように「療法」をイメージし、あるネットによると「人間が本来もっている力を引き出して不安を解消すること」とでています。その解決に向かうために本人の言葉を使うのはよく理解できますし、SFとの親和性も理解しているつもりです。
また、アプリシエートやタロットによって自己を深く見つめたり、無意識を顕在化することによる振り返りも次のステップへの大きな力となることも想像できます。
またこれらのしくみを知らないより、知っているほうがSFや人への理解は深まるというふうに思います。
しかし、ひょっとして人はそれを知らなくてもなんらかの方法で自分自身に取り入れることができるのかもしれないなあと浮かんできました。(できにくい状態もあるでしょう)
渡辺さんの研究によると、研究対象の係長さんたちはコーチングを受けることによって自然と自身の中に内省の心を生み出し、コーチングの技も身につけながらきちんと自分自身で自分自身のあるべき姿をつかんでおられました。
青木さんの最近の取り組みや渡辺さんの研究は一番シンプルなSF(フューチャーパーフェクトにスモールステップで)というものの持つ底知れないパワーを証明しているように見えてきます。僕のような凡人にはセラピーや人間というものを理解できていなくてもSFという船に乗っかっていれば自然とその奥深さをも手に入れたごとく、前を向く勇気が湧いてくるのはありがたいことなのです。きっと全てはどこかでつながっているんですよね。合掌!
決して青木先生やプラーメン博士の活動を否定するものではありません。
おっくん
おっくん、いつもコメントありがとうございます。「一つ質問しても・・」の後に質問が見つからなかったので回答はできませんが、おっくんが書いたことはその通りだと思いますよ。
人と人がどのように接することで何が起こるかに関する知恵は、セラピー、占い、コーチング、対話、会話、酒の席の放言、その他どのような名前がつけられようが、有効なものは有効だと思いますし、それが教育の結果なのか、先天的な才能なのか、その両方なのかの割合は色々でしょうけど、人間がもともと潜在的可能性として持っているものだと思っています。
セミナーをやっていると、表面上は教えるという立場、学ぶという立場の区別がありますけど、結局教え合っているよねえと、先日僕が通っているボイトレの先生と意見が一致しました♪
でもやっぱり、見えてないもながあるのなら見えるように手助けしてあげることは素敵なことですね。
とりとめのないコメントにもOKいただき、恐れ入ります。
いつもおっくんのコメントからは刺激をいただいています!ありがとうございます。